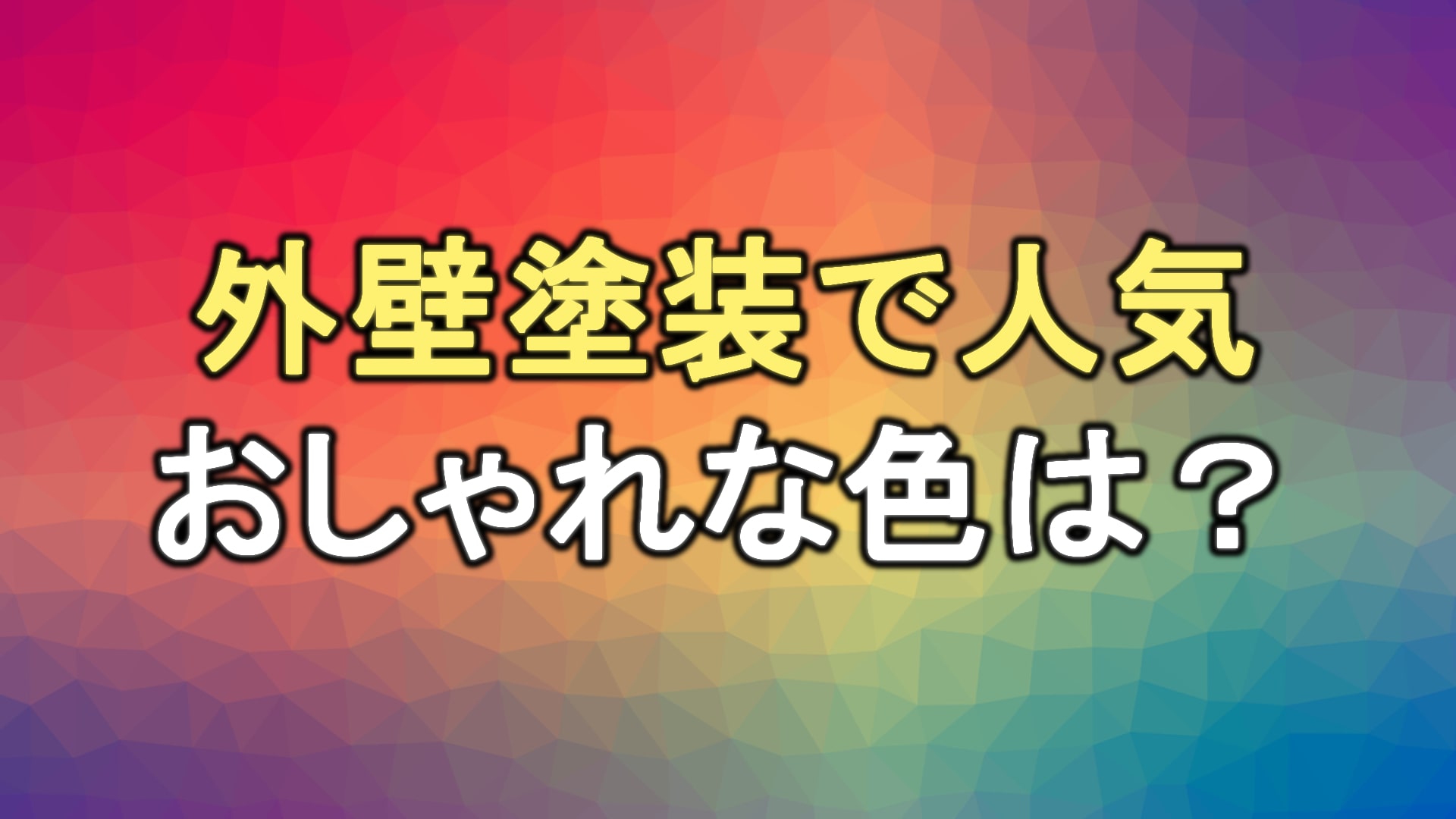外壁に繁殖した苔を
自分で取る方法はありますか?
公開日: 2020年04月30日 / 更新日: 2025年08月04日
苔の掃除は、それほどやっかいではありません。外壁が緑色に着色したように見える苔は、洗剤とブラシで落とすことができます。専用洗剤を使ってもいいでしょう。


意外と簡単に落ちます。
低いところなら自分でやってみましょう!
簡単に落ちると言ってしまいましたが、苔にも種類があります。
ここで言うのは、上の画像のように外壁が緑色に着色したような苔を指していると思ってください。
モルタルやサイディングの外壁に生える苔は、ほとんどがこのタイプです。
こんもり茂っている場合は、まずスクレーパーなどで剥がす作業が必要になりますが、一軒家のモルタルやサイディングに、神社の石段のような苔が生えることはほとんどありませんので今回は除外します。
植物(苔・藻)か、カビかを判断しよう
外壁に生えている緑色の物体ならだいたい苔ですが、黒っぽい苔もありますし、苔が枯れた状態で茶色になることもあります。
そうなると、遠目にはカビと見分けが付かない場合もあります。
外壁に取り付くこれらは、大きく三つに分類できます。
- 1 苔
- 2 藻
- 3 カビ
除去の仕方はどれもほとんど同じですが、何が生えていたのかによって、後の対処法が変わります。
いきなり掃除せずに、原因が何だったのかを知っておきましょう。

たとえばこの黒い物体。ぱっと見はカビのようにも見えます。
とっても簡単な見分け方は、近づいてよく観察すること……。

おそらくこれは、苔か藻です。私たちは植物学の専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、「見ればわかる」ことがほとんどです。
みなさんもなんとなーく「植物っぽいな」と思いませんか?雑ですみませんね~!
よくわからない場合は、外壁の立地条件で見分けます。
苔や藻は植物なので、光を必要とします。
しかし、カビは菌類なので光を必要としません。
日光が当たる場所なら植物(苔・藻)、当たらない場所ならカビの可能性が高いです。

こちらのお宅の写真では、奥の壁が緑色になっています。光があたる場所で、なおかつ湿気が溜まりやすい場所に苔が生えます。
自分で苔・藻を取れるのは、手が届く範囲だけ
前提として、手が届く範囲の作業とします。
高所の作業の場合は、ご自身でやるのを諦めてください。脚立を使っての作業は特にいけません。
理由はこちらの記事にまとめました。
→「外壁にツタが繁殖しています。自分で取る方法はありますか?」
手が届かないところの掃除は、プロに依頼してください。
足場を組む必要があるので高額になります。外壁塗装、修繕などと合わせて行うことをお勧めします。
自分で取るなら、ブラシと中性洗剤で
水洗いだけでもかなり苔は落とすことができます。ホースで壁に水をぶっかけて、ブラシで擦ってみましょう。
ブラシは、握りやすく硬すぎないものなら何でもかまいません。
硬いものは傷が付きます。洗車用、お風呂用などが良いでしょう。

落ちにくいようなら、食器用洗剤を使います。バケツに洗剤を溶いた水を用意しておき、ブラシにつけながら擦ります。
界面活性剤の働きで落ちやすくなります。
苔専用洗剤の実力は?
専用洗剤をホームセンターやAmazonで買うこともできます。
「墓石用洗剤」とあるものも、主に苔を落とす効果を狙った商品です。
これらを試してみてもいいでしょう。
一番上の写真にあるような薄い緑の苔なら、けっこう効果があります。
ただし、「スプレーするだけで擦らず落ちる」という商品はちょっと誇張だと思います。
スプレーするだけで苔が物理的に消える(溶ける)ような強力な薬剤は、市販できません。
「スプレーするだけで苔が枯れる」はありえます。
薄い苔は擦り落としてしまえばいいので枯らす工程は要りませんが、しつこい苔の場合は剥がしやすくなると思います。
苔専用洗剤の選び方
農薬は大きく二種類あり、全部の植物を枯らすタイプ、特定の植物を枯らすタイプがあります。
後者のタイプは、薬剤の種類が本当に多いです。
作用機序によっても薬剤が異なるので、「○○入りと書いてあるものがいいですよ!」と簡単に言えません。
厳密には、苔の種類ごとに薬剤が違うはずだからです。
ひとつ言えるのは、塩素系のものは避けるべきだということです。
外壁が変色する可能性があります。
やらない方がいいこと
- 熱湯、ハイター、塩、酢をかけること
- 高圧洗浄機で掃除すること
昔から、熱湯、ハイター、塩、酢は雑草を枯らすために有効と言われていますが、おすすめしません。
熱湯はすぐに冷めてしまうのでほとんど効果がありません。
地面の雑草に対しても効果がないので、すぐに流れ落ちてしまう壁であればなおさらです。
また、火傷の恐れがあるのでやめましょう。
ハイターは、次亜塩素酸ナトリウムでできています。上に述べた「塩素系」の代表格です。
アルカリ性が強く、漂白作用があるので外壁を傷めてしまいます。
塩も外壁を傷めるので使ってはいけません。
酢は、アクアリウムをやっている方にはお馴染みの方法です。
食用酢、木酢液、クエン酸を使って苔を除去するのはよくある手です。
ですが、外壁のように広範囲の場所に使うのはあまり適さないでしょう。
アクアリムで苔の除去に酢を使うのは、枯らしたくない水草と、枯らしたい苔が水槽内に混在しているためです。
魚に影響が少ない酢を、苔にだけ塗ることで苔を減らします。
外壁の苔を除去するなら、食器用の中性洗剤で擦った方が早いです。
家庭用の高圧洗浄機でも、外壁が傷んでいる場合は傷を増やしてしまうのでおすすめしません。
プロはどうやって落とすか
プロも、軽微な苔なら作業としては同じです。水、洗剤、擦る。以上。
高所作業ができること、外壁の状態を見極められるのがプロに依頼するメリットです。
プロは、頑固な苔には業務用の高圧洗浄機を使うこともあります。必要なら、業務用のバイオ洗剤を使用します。
ただし、高圧洗浄機は威力が強すぎるので、外壁が傷んでいる場合は腐食した部分まで剥がれたり、最悪の場合は外壁にヒビが入ることがあります。
闇雲にやっていいことではありません。
往々にして、苔が繁殖しているということは外壁が傷んでいることなので、まずは外壁の診断をし、適切な対処法をアドバイスいたします。
残念ながら、苔は再発します!
苔も藻もありふれた植物なので、風にのって胞子がやってきて定着してしまえば元の状態に戻っていきます。
定着させないようにすることが大事ですね。
苔の予防については、こちらにまとめました!
→「苔を生えにくくする方法はないのでしょうか?」
以上、和田がお答えしました!
外壁に苔が生えやすい住宅の特徴
外壁にコケが発生するには、いくつかの明確な理由があります。
コケも生き物であるため、彼らにとって「住みやすい環境」が揃ってしまうと、どうしても繁殖しやすくなるのです。
まず、最も大きな要因となるのが「日当たり」と「風通し」です。
コケは、湿気を好む植物であるため、日光が当たりにくく、常にジメジメしている建物の北側や、隣家との間が狭く、風が通りにくい場所は、絶好の繁殖ポイントとなります。
また、川や田んぼ、公園、森林などが近くにある場合も、空気中の湿度が高く、コケの胞子が飛んできやすいため、注意が必要です。
さらに、外壁材そのものの特徴も、大きく影響します。
リシンやスタッコといった、表面に凹凸のあるザラザラとした仕上げの外壁は、その溝に水分や、胞子、ホコリといった栄養分が溜まりやすく、コケの温床となりやすいのです。
参考記事:外壁の苔を防ぐ方法
苔の放置で起こる住宅の劣化症状
外壁に生えたコケを、「ただの緑色の汚れだから」と、軽く考えて放置してしまうのは、非常に危険です。
コケは、単に建物の美観を損なうだけでなく、その防水機能や耐久性を、内側から静かに、しかし着実に蝕んでいく、厄介な存在です。
建物内への浸水
コケは、その体内に常に水分を保持する性質を持っています。
つまり、外壁にコケが繁殖しているということは、壁の表面が、24時間365日、湿ったスポンジで覆われているような状態だということです。
この水分は、外壁を保護している塗膜を、常に湿潤な状態に保ち、その劣化を著しく早めてしまいます。
やがて、防水機能を失った塗膜を突き破り、水分は外壁材そのものへと浸透していきます。
そして、壁の内部にまで水が達すると、断熱材を機能不全に陥らせ、最終的には、雨漏りという、最も深刻な事態を引き起こす原因となります。
コケのさらなる増殖
一度発生したコケを放置すると、事態はさらに悪化していきます。
コケ自体が、さらに水分や、ホコリなどの栄養分を溜め込む、格好の「温床」となるからです。
これにより、コケは、より根深く、そしてより広範囲へと、その勢力を拡大していきます。
初めは小さな緑の斑点だったものが、いつの間にか壁一面を覆い尽くす、ということも珍しくありません。
また、劣化したコケは、カビなどの、他の菌類の栄養源ともなります。
コケとカビが複合的に発生することで、外壁の劣化スピードはさらに加速し、建物の寿命を、大きく縮めてしまうという、負のスパイラルに陥ってしまいます。
外壁の苔発生を予防するポイント
一度、根を張ってしまったコケを完全に取り除くのは、大変な労力を要します。
そこで重要になるのが、そもそもコケを発生させないための、予防的な対策です。
ここでは、ご家庭でできることから、専門的な方法まで、5つの予防ポイントをご紹介します。
外壁の前に物を置かない
ご家庭で、すぐにでも実践できる、最も簡単な予防策です。
外壁のすぐ前に、物置や、使わなくなった植木鉢、ゴミ箱などを置いていると、その部分の風通しが著しく悪くなり、湿気がこもる原因となります。
コケは、こうしたジメジメした場所を好んで繁殖します。
壁と物の間に、十分なスペースを確保し、空気の通り道を常に作ってあげる。
たったこれだけの工夫で、コケの発生リスクを、大きく低減させることができます。
住宅を選ぶ際に森林が近い場所を避ける
これは、これから家を建てる、あるいは購入する際の、土地選びの段階でのポイントになります。
前述の通り、森林や林、あるいは大きな公園などが隣接している土地は、空気中の湿度が高く、また、コケの胞子も飛んできやすい環境です。
もちろん、緑豊かな環境は、多くの魅力がありますが、同時に、建物にとっては、コケが生えやすい条件下にある、ということも、念のため理解しておくと良いでしょう。
すでに、そうした環境にお住まいの場合は、より一層、こまめな点検や、後述する高機能な塗料での予防が重要になります。
凹凸が少ない模様を選ぶ
外壁材のデザインも、コケの発生しやすさに影響します。
ヨーロッパ風の住宅で人気の、リシンやスタッコといった、表面がザラザラとした、凹凸の大きい仕上げ材は、その意匠性が高い一方で、溝の部分に、水分や汚れが溜まりやすいという弱点があります。
これが、コケの繁殖の温床となってしまうのです。
もし、コケの発生を、できるだけ抑えたいと考えるのであれば、外壁材には、比較的表面がフラットで、凹凸の少ないデザインのものを選ぶ、というのも、一つの有効な選択肢となります。
光触媒塗料を使用する
ここからは、外壁塗装による、専門的な予防策です。
「光触媒塗料」は、塗料に含まれる酸化チタンが、太陽の光(紫外線)に反応し、外壁に付着した汚れを、分解する力を持つ、非常に高機能な塗料です。
さらに、光触媒の膜は、水に馴染みやすい「超親水性」という性質も持っているため、雨が降ると、分解された汚れが、壁と塗膜の間に入り込んだ雨水によって、きれいに洗い流されます。
このセルフクリーニング効果により、外壁を、長期にわたって、汚れやコケのない、美しい状態に保つことができるのです。
防カビ性の高い塗料を使用する
最も直接的で、効果的なコケ対策が、防カビ・防藻性に優れた塗料を選ぶことです。
これらの塗料には、コケやカビの繁殖を、長期間にわたって抑制する、特殊な薬剤が配合されています。
現在、多くの大手塗料メーカーが、この防カビ・防藻機能を備えた塗料を、標準的にラインナップしています。
外壁塗装を行う際に、塗料のグレードを選ぶだけでなく、こうした「付加機能」にも着目することが、将来的なメンテナンスの手間と、コストを抑える上で、非常に重要になります。
特に、日当たりの悪い北面など、コケが生えやすい部分に、こうした高機能な塗料を使用するのは、極めて有効な対策といえるでしょう。
参考記事:「何度も外壁塗装したくない!」長持ち・コスパ最強の外壁塗料とは?
狭山市・川越市・所沢市で外壁塗装なら株式会社喜多建設にお任せください
外壁塗装はどの業者に依頼するかで、仕上がりや満足度が大きく変わります。株式会社喜多建設は以下の理由で多くのお客様からご支持をいただいています。
創業100年の地域密着で迅速対応
狭山市・川越市・所沢市を中心に地元の気候や住宅事情に詳しいため、最適な塗装プランをご提案できます。
自社施工で中間マージンなし
営業から施工、アフターフォローまで自社一貫対応。安心価格で高品質な塗装を実現しています。施工するすべての塗装に10年保証をお付けしております。
確かな技術と安心のサポートが当社の売りです。ぜひお気軽にお問い合わせください。
監修者
-

-
喜多 史仁
株式会社喜多建設 代表取締役社長
<略歴>
高等学校を卒業後に、2代目有限会社喜多塗装店(株式会社喜多建設の前身)に塗装見習いとして入社。その後、大手自動車メーカー子会社を経験し、2000年に3代目有限会社喜多コーポレーションに職長及び取締役として入社。
2007年に社名を株式会社喜多建設に変更を機に代表取締役に就任。
埼玉県狭山市・川越市・所沢市を中心に地域に密着した外壁塗装を強みとしています。<喜多建設のこだわり>
喜多建設では、不安や疑問を持った状態で外壁塗装をすることがないようにお客様への丁寧なご説明をモットーとしております。
株式会社喜多建設の取り組みはこちらから
このページに掲載するかどうかはお約束できませんが、お問合せには必ずお返事しております。
何でもお気軽にお問合せください。