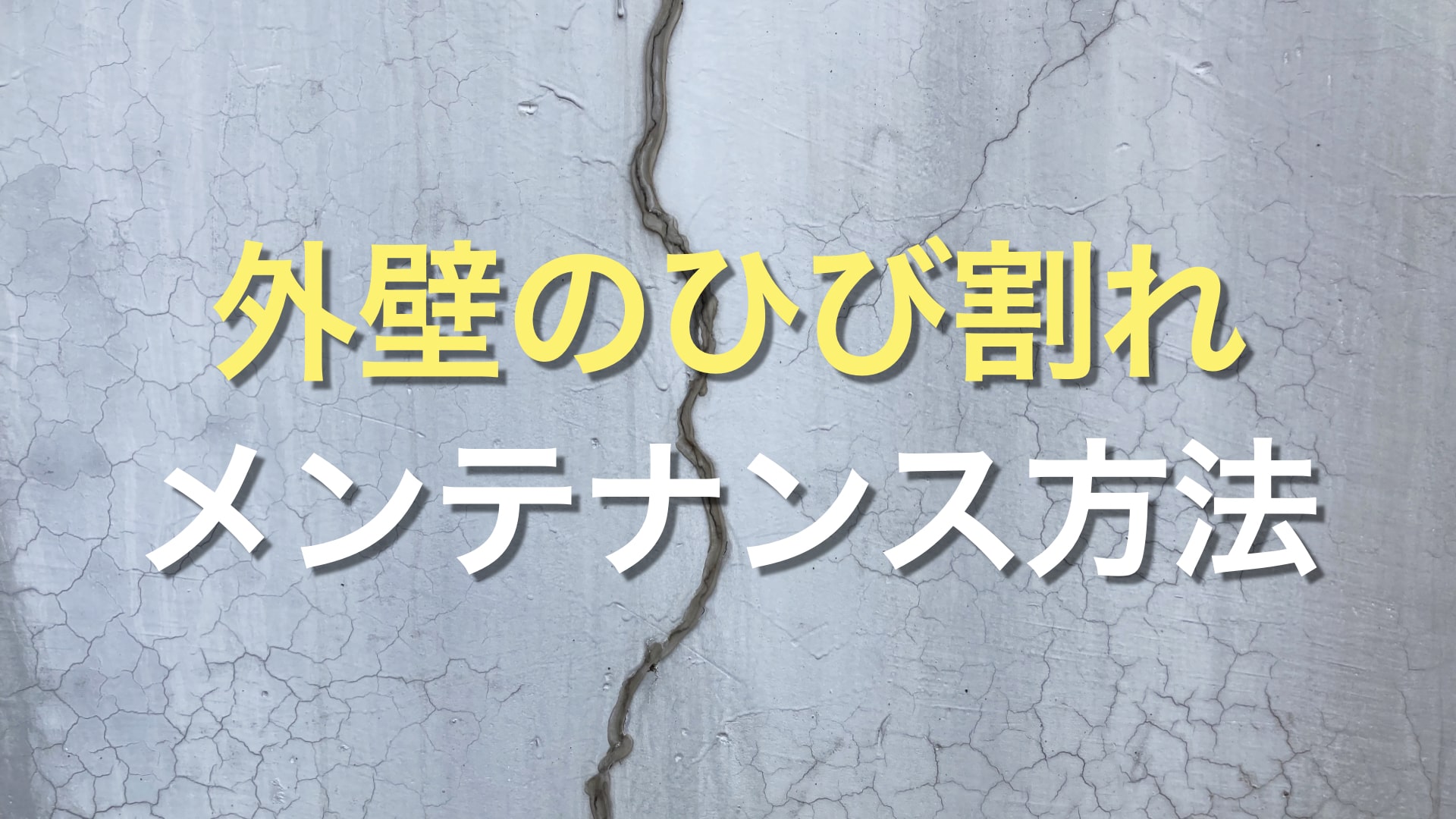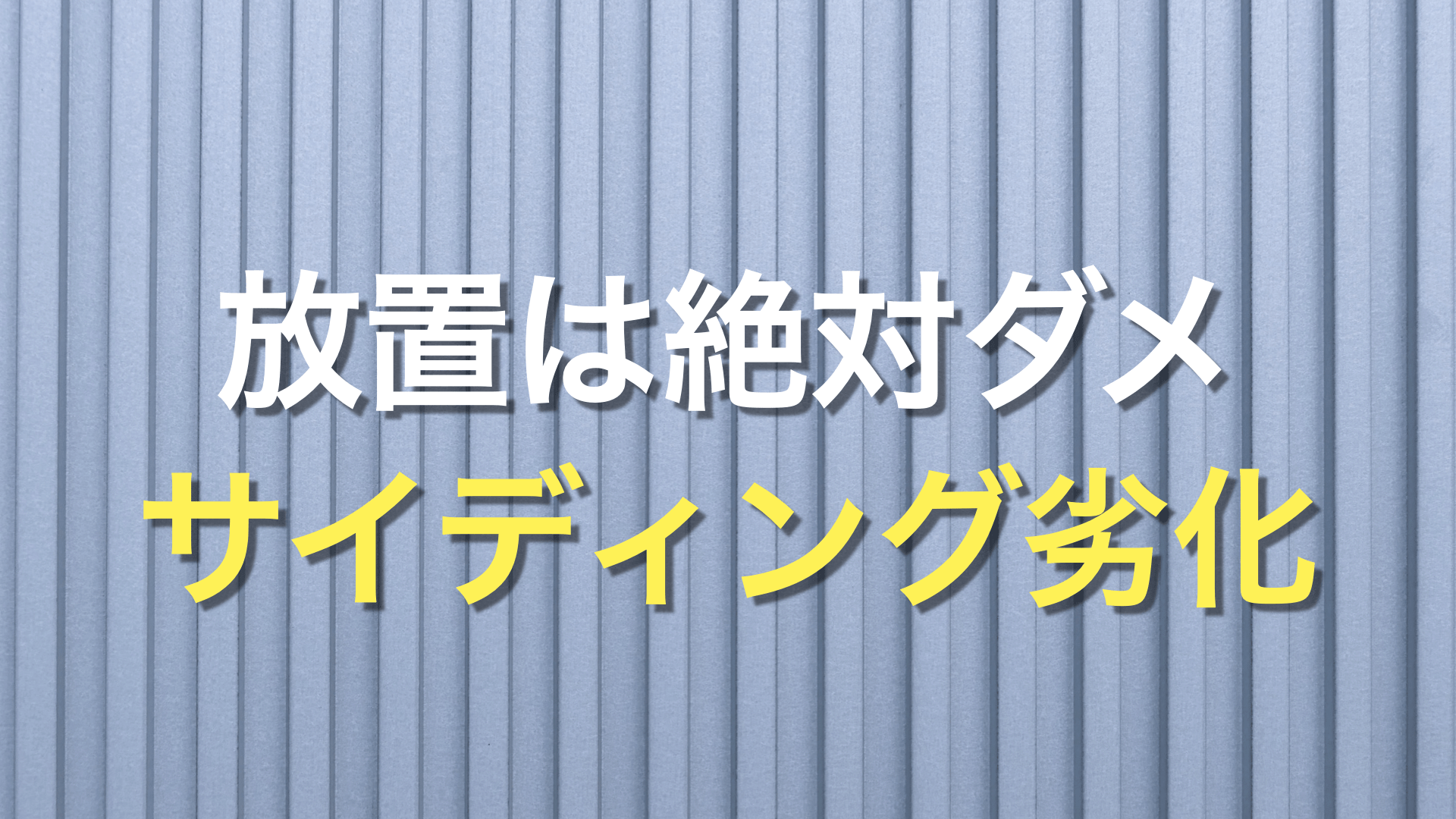パミール屋根だから塗装できないって言われたけど、どうすればいいの?
ウチの屋根は、本当にパミール屋根なの?
公開日: 2022年03月21日 / 更新日: 2025年03月29日
パミール屋根だから、塗装ができないと言われても、どうしたらいいのかと困ってしまいますよね。
パミール屋根は現在製造中止となっている屋根材ですが、2008年まで製造されていたので、未だ多くの住宅に使用されています。
さらに、塗装ができない屋根としても有名で、メンテナンスをする際には別の工法でなければなりません。
一体どのようにして、メンテナンスを行っていけばいいのでしょうか?
今回は、パミール屋根の見分け方やメンテナンス方法についてご紹介します。
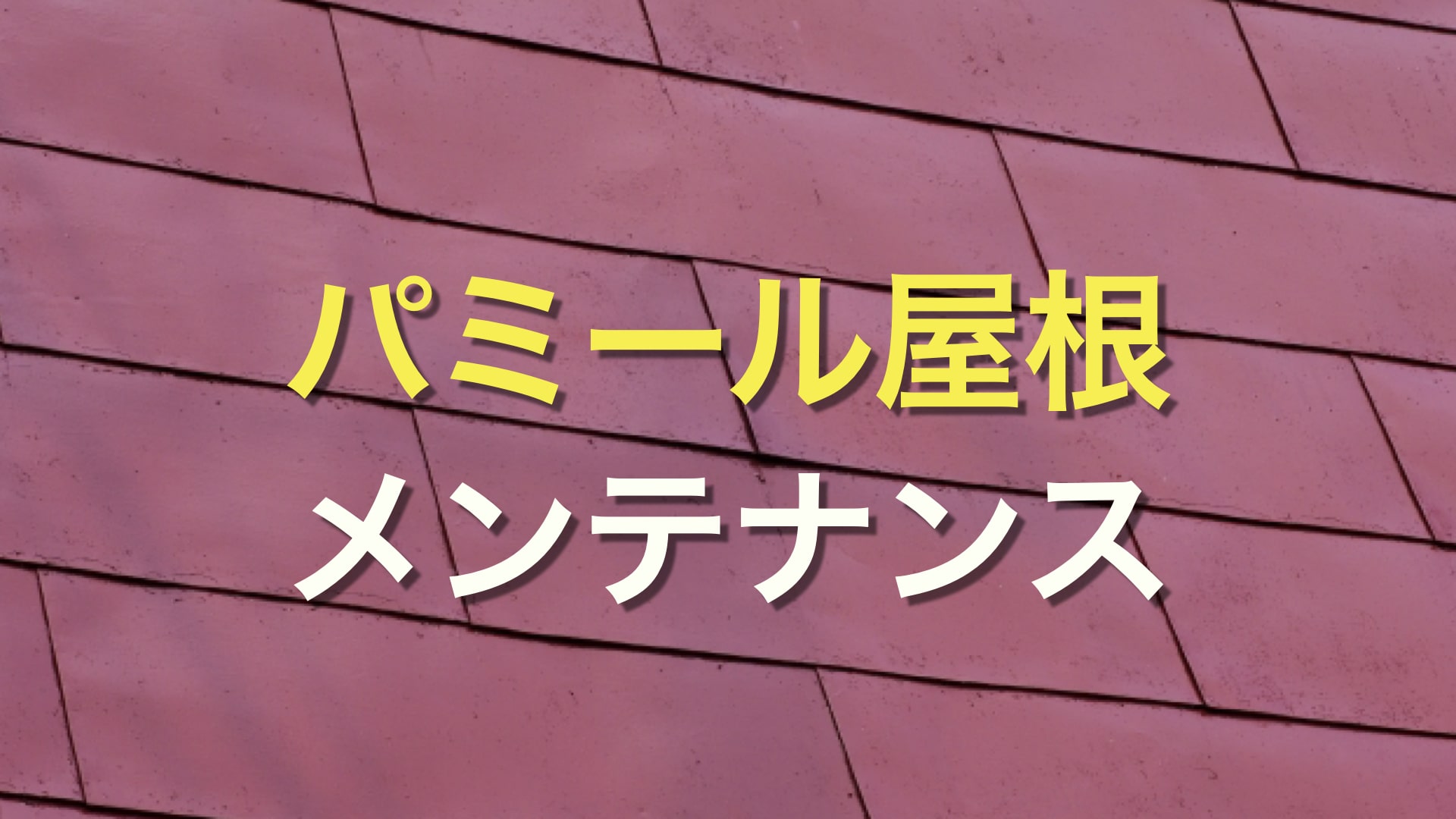

パミール屋根は塗装ができません。
理由は、塗装をしても屋根ごと剥がれてしまうからです。
おすすめできるメンテナンス法は、「葺き替え工事」になります。
パミール屋根かどうかの見分け方は、劣化症状で判断できます。
パミール屋根は塗装ができない
パミール屋根は、塗装をしても屋根材が剥がれてしまうため、意味がありません。
一般的には、塗装の前に高圧洗浄を行います。
しかし、パミール屋根は高圧洗浄でも屋根材が剥がれてしまうため、洗浄もできません。
もし、パミール屋根と知らずに塗装を依頼してしまうと、劣化が進みさらに高額なメンテナンス費用が必要となってしまいます。
パミール屋根の見分け方とは?
パミール屋根の見分け方についてご紹介します。

屋根の劣化症状で判断できる
屋根材の劣化症状で、パミール屋根と判断することができます。
他の屋根材とは違い、特徴的な劣化症状があるため、劣化が進んでいるときには見た目で分かります。
主な劣化症状としては、屋根材が剥がれたり、使用している釘が腐食するということが挙げられます。
放置していると、屋根がボロボロになってしまうため、早急にメンテナンスが必要です。
製造中止となった理由の1つは、耐久性の問題です。
パミール屋根は、7年ほどで屋根が剥がれてきてしまい、10年ほどで劣化症状がかなり進行してしまいます。
業者に依頼して、判断してもらう
パミール屋根かどうかを判断するには、業者に依頼することをおすすめします。
劣化症状で判断できるとお伝えしましたが、屋根に登って確認することはとても危険です。
適切な判断をするためにも、業者に依頼して確認してもらいましょう。
パミール屋根の特徴的な劣化症状
パミール屋根かどうかの判断基準になる劣化症状についてご紹介します。
特徴的な劣化症状は以下の通りです。

層間剥離
屋根材がパリパリと剥がれていく症状を「層間剥離」と言います。
密着性に問題が発生し、ミルフィーユのように層が分かれる状態になってしまいます。
パミール屋根の特徴的な劣化症状です。
パミール屋根は吸収性が高いため、雨水や雪などの水分を吸収して乾燥するたびに伸縮を繰り返します。
その結果、層間剝離が起きてしまいます。
屋根材ごと剥がれてしまうため、放っておくと内部も劣化してしまい、雨漏りの原因となります。
釘の腐食
パミール屋根に使用されている釘の腐食も特徴的な劣化症状の1つです。
釘が腐食してしまうと、屋根がズレてきてしまいます。
最悪の場合は、屋根材が剥がれ落ちてしまい、近隣建物を傷つけてしまったり、事故が発生してしまうことも考えられます。
釘が腐食してしまう原因は、製造元のメッキ処理の薄さです。
メッキ処理が薄い釘を使用すると、サビや腐食が発生しやすくなります。
製造元であるニチハも公表している事実であり、製品のなかにメッキ処理が薄いものが含まれていたようです。
パミール屋根のメンテナンス方法
パミール屋根は塗装ができない屋根材となりますので、メンテナンスをする際には「葺き替え工事」がおすすめです。
「カバー工法」もメンテナンス法として挙げられますが、正直なところこの工法はおすすめできません。
こちらでは、パミール屋根に適しているメンテナンス方法についてご紹介します。

【葺き替え工事】パミール屋根に最適なメンテナンス方法
パミール屋根をメンテナンスする際に、一番おすすめできる方法は「葺き替え工事」になります。
葺き替え工事とは、既存の屋根材を剥がし、新しい屋根材に張り替える工事です。
パミールを全面撤去するため、メンテナンス後のリスクを考える必要はありません。
メンテナンス時に、耐久性に優れているものや耐用年数が長い屋根材を選定するようにしましょう。
高耐久性の屋根材に張り替えると、次回のメンテンナスは20年~30年先となり、費用をかける必要がなくなります。
業者から他の方法を勧められるかもしれませんが、長い目で見ても葺き替え工事がおすすめとなります。
【カバー工法】結露ができてしまう恐れがある
屋根材のメンテナンス方法として、「カバー工法」が挙げられますが、パミール屋根には適しているとは言えません。
カバー工法は、既存の屋根材の上から防水シートや新しい屋根材を張るメンテナンス法です。
外壁含めこの工法が適している場合もありますが、パミール屋根の場合は結露ができてしまう恐れがあります。
後に、再度メンテナンスが必要となり、さらに高額な費用が掛かってしまうことも考えられます。
結露ができてしまう理由としては、パミールが吸収性が高く、メンテナンス時にはかなりの水分を含んでいるからです。
水分を多く含んでいる屋根材の上から新品の素材でカバーしてしまうと、乾燥が充分に行われず水分が残ったままになってしまいます。
結露をそのままにしていると、サビが発生してしまい、屋根材が朽ちてしまうリスクもあります。
まとめ
2008年まで製造され使用されていたパミール屋根は、メンテナンスで再塗装を選択することができません。
自宅の屋根がパミール屋根であるかどうか確かめるには、劣化症状で判断できます。
ただし、自己判断するには危険なこともあるため、業者に依頼して判断してもらうようにしましょう。
劣化症状が進んでいる場合は、葺き替え工事で屋根材を新しく丈夫なものに張り替える必要があります。
屋根材のメンテナンス方法としては、他の工法もありますが、素材に適した方法を選ばなければなりません。
間違った方法でメンテナンスを行うと、後に再度メンテナンスが必要となり、費用も高額になります。
もしかして、自宅の屋根がパミールかもしれないという可能性がある場合は、今回の記事を参考にしてみてください。
監修者
-

-
喜多 史仁
株式会社喜多建設 代表取締役社長
<略歴>
高等学校を卒業後に、2代目有限会社喜多塗装店(株式会社喜多建設の前身)に塗装見習いとして入社。その後、大手自動車メーカー子会社を経験し、2000年に3代目有限会社喜多コーポレーションに職長及び取締役として入社。
2007年に社名を株式会社喜多建設に変更を機に代表取締役に就任。
埼玉県狭山市・川越市・所沢市を中心に地域に密着した外壁塗装を強みとしています。<喜多建設のこだわり>
喜多建設では、不安や疑問を持った状態で外壁塗装をすることがないようにお客様への丁寧なご説明をモットーとしております。
株式会社喜多建設の取り組みはこちらから
このページに掲載するかどうかはお約束できませんが、お問合せには必ずお返事しております。
何でもお気軽にお問合せください。